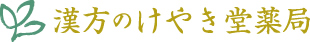【ブログ】心と体が疲れやすいときに。気の巡りを整える東洋医学の知恵
最近、増えているご相談の一つに自律神経の症状があります。
東洋医学(中医学)でいう「気滞(きたい)」に関係しています。
東洋医学でいう「気」は、生命活動を支えるエネルギーであり、特に「肝(かん)」の働きによって全身を巡ると考えられています。この「肝」の働きは、ストレスや感情の影響を受けると、乱れてしまいます。その結果、気の巡りが停滞し、気滞になります。不眠、自律神経失調症、生理不順、更年期症状の悪化、胃腸の不調、うつ様状態などの要因になると言われています。
通常、適度な緊張やストレスは、やる気や成長の原動力となり、達成感や高揚感をもたらします。資格の勉強やスポーツなどが当てはまるでしょう。その一方で、過剰な仕事のプレッシャーや、慢性的な人間関係のストレスなど、自分でコントロールのしにくい精神的負担が続くことで不調につながると言われています。
近年では、ストレスが長く続くことで脳内に活性酸素が溜まり、血中コルチゾール(血糖、血圧を上昇させて、ストレスに対応するホルモン)濃度が上昇してしまうことや、過剰な活性酸素で細胞内のミトコンドリア(細胞内のエネルギー工場の役目)を傷つけることで、ミトコンドリアの機能を低下させ、破壊することが分かっています。これらのことで、心身の不調が長引いてしまう要因であると考えられています。
Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 117(2009)50-55
片岡 洋祐 脳の疲労と酸化ストレス Functional Food Vol.3,No.4(2010)
気の流れを良くして心身を調えるには、
・軽い運動(深呼吸や速歩など)
・ストレッチ
・歌を歌う(声を出す)
・ぬるめの湯船に浸かってゆっくり入浴
・好きな香りを楽しむ(グレープフルーツやラベンダーなど)
・視点を変えてみる。自分を慰めたり楽しくしたりする工夫をしてみる
といった、日常の中で取り入れやすい方法が役立ちます。
ぜひ参考にしてみてください。
その一方で、就寝前のインターネットやSNSなどの閲覧は、刺激の強い情報が心身の緊張を高めてしまうことがあるため、避けましょう。
漢方薬では、一般的に、四逆散、香蘇散、逍遥散、柴朴湯、半夏厚朴湯などを用います。
また、カウンセリングでは、お客様がお話をされることで、気づきを得たり、気持ちが整理されたりすることも多いです。どうぞお気軽にご相談ください(要予約)。(岡北)
【ブログ】日常生活でできる認知症予防 4つのポイント
認知症(特にアルツハイマー型)の発症には、動脈硬化やそれに伴う脳血流の低下が大きく関与することが知られています。
漢方では、当帰などの生薬の力を活かした血行対策が、認知症の発症予防に活用できると考えられています。パナパール錠(剤盛堂薬品、第3類医薬品)で、健常~軽度認知障害(MCI)までの人の認知症予防効果が確認されているそうです。パナパール錠は、虚弱体質・肉体疲労・病中病後・胃腸虚弱・食欲不振の症状を改善し、滋養強壮のために考え出された生薬製剤です。抗認知症薬としても特許を取得しています。
軽度認知障害(MCI)とは、健康な状態と認知症の間にある“認知症の前段階”のことをいいます。
認知症の約6割はアルツハイマー型とされ、MCIと診断されてから3〜5年ほどで認知症へ進行する方が多いといわれています。進行のしかたは、生活習慣病や疲労、うつ病、睡眠障害の有無など心身の状態によっても変わるそうです。できるだけよい状態を維持するために、日常生活を見直しして心身を健やかに保つことが大切です。
今回は、日常生活で取り入れやすい予防法を4つご紹介します。今、MCIでない方にも、生活を見直す上では、よい方法だと思います。
(1)有酸素運動を取り入れる
ウォーキングなどの有酸素運動は、体に酸素を取り入れながら行うため、脳への血流が良くなり、認知症予防に良いそうです。信州大学の能勢博教授によると、「インターバル速歩」で特にMCIの人の34%に認知機能の改善が見られたと報告しています。
インターバル速歩とは、速歩3分+ゆっくり歩き3分を1セットとして、
1日5セット、週4回以上行い、5か月以上続ける方法です。速歩は、ややきつい程度が目安。
買い物やペットの散歩は、全く運動しないよりは良いのですが、運動としての効果はあまり高くないと言われています。運動中にしりとりをするなど、頭を使いながら行う、「ながら運動」も効果的です。持病のある方やリハビリ中の方は、運動の強さについて主治医やリハビリの先生にご相談ください。
(2)睡眠の質を良くする
良い睡眠は、心と体の健康に大切です。眠りはじめに訪れる深い睡眠の時間には、成長ホルモンが多く分泌されるそうです。このホルモンは体の修復だけでなく、代謝機能の調節や、免疫の維持、認知機能の維持にも関係しているといわれています。
夕方のうたた寝や、テレビやスマホなどを見ながらの寝落ちは、夜の深い睡眠を妨げることがあります。うたた寝や寝落ちを避け、夜にしっかり眠れるよう生活リズムを整えましょう。
(3) 栄養バランスの良い食事
体も脳も食べ物で作られています。一般的に、年齢を重ねると、食事量が少なくなり、味覚も鈍くなってきます。よく噛んで食べ物が消化管から吸収されるように食べるようにしましょう。
特におすすめなのは、
・野菜や果物、全粒穀物などの食物繊維を多く含む食材
・魚、特にマグロ、カツオ、サバ、イワシ、サンマなどの背の青い魚
・脂肪の少ないたんぱく質 鶏肉、豆腐、納豆などの大豆製品などです。
(4)社会活動に参加する
人と話したり、地域の活動に参加したりすることは、脳を活性化させ、認知症の進行を抑える効果があるといわれています。友人とのおしゃべり、趣味の集まり、ボランティアなど、なるべく外に出る機会を作ってみましょう。
(1)-(4)は、NHKきょうの健康2023.1、2024.9、2025.9健康長寿ネット インターバル速歩、書籍「もしかして認知症?」浦上克也(著)を参考にしています。
アルツハイマー型認知症の原因の一つとされるアミロイドβというたんぱく質は、物忘れの症状の出ていない40代後半から脳内に蓄積が始まるといわれています。発症までに20-25年という長い年月を経て発症するそうです。
毎日の食事や運動などの心がけに加えて、嫌なことは深く考え過ぎずにけろっと忘れ、楽天的に考える習慣を持つことで、心も体も健やかに保つことができるものと考えています。(岡北)
【ブログ】正月に飲む、お屠蘇について
日本では正月に一年の無病息災と長寿を願い、お屠蘇を飲む習慣があります。一般的には、屠蘇散を日本酒に浸してお屠蘇を作ります。屠蘇散は、製造会社によって生薬や、配合量が少しずつかわります。胃腸をいたわり、邪を取り除く成分(抗炎症、排膿作用、発散作用など)で構成されています。
お酒が苦手な方や、運転される方、お子様などお酒を控えている方には、屠蘇散を「薬膳茶」として楽しんでいただけます。
屠蘇散のティーパックを白湯(お好みに合わせて200-500ml)に3分ほど浸し、ティーパックを取り除いてからお飲みください。
香りが良く、体をやさしく温めてくれるお茶ですので、ぜひお試しください。

【ブログ】第35回 大阪むらさきクラブの集い 健康講演会を開催しました
11月9日(日)、大阪市天王寺にある「あべのハルカス」にて、健康講演会「第35回 大阪むらさきクラブの集い」を開催いたしました。
あいにくの雨模様にもかかわらず、多くの皆様にご来場いただき、心より感謝申し上げます。
この集いは、今年で35回目を迎える歴史あるイベントで、参加を希望されたお客様にお越しいただいております。大阪府内の自然薬研究会に所属する薬店・薬局の有志と協力し、企画・運営を行っています。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催を見送った時期もありましたが、前回より再開し、今回はコロナ後初めて多くの方々にご参加いただくことができました。

当日は、医師・山岡傳一郎先生による「フレイル」に関するご講演をはじめ、お客様の体験談、自然薬の解説、お楽しみ抽選会、そして最後には「みんなありがとう」の歌をお届けしました。

お客様のご参加と、ご支援・協力してくださった方々のおかげで、心温まるひとときを共有することができました。改めて、厚く御礼申し上げます。


【ブログ】寒暖差に負けない!冷えと不調を防ぐ冬の養生法
寒暖差が大きくなるこの季節は、頭痛やめまい、倦怠感、肩こり、不眠、気分の落ち込み、便秘や下痢などの症状が現れやすくなります。これは、自律神経の働きが乱れ、体温が下がり、内臓の機能が低下することが原因とされています(※1)
私事ながら、私自身は秋から冬にかけての寒暖差に弱く、寒さや乾燥からのどを痛めやすいので、日頃から規則正しい生活を送るようにし、漢方も取り入れています。
冷え対策には、まず手首・足首・首まわりの3つの首を保温することをお勧めしています。この3首は、皮膚が薄く、太い血管も通っているので、冷えやすい場所ですが、保温することで、体の熱を外に逃がしにくくなります。長そでの下着やレッグウオーマーを使うのが有効だと思います。
また、尾てい骨の上にある仙骨(背骨の一番下にある三角形の骨)に「八髎(はちりょう)」という8つのツボがあります。下着の上から、この仙骨のあたりに下着の上からカイロを貼ることで、交感神経の緊張を和らげ、下腹部の血流を改善することが出来ます(※2)
私も毎年、気温が下がり始めた頃から仙骨のあたりに薄型のカイロをはっています。下着1枚重ねて着る以上の保温効果があると感じています。注意点として、低温やけどに気を付けて、熱くなってきたら、はがすこと、就寝中は使用しないようにすることの2点を守ってください。
急いで体を温めたい時には、しょうが湯、または葛湯(くずゆ)、湯で溶いた葛根湯(かっこんとう、当店では「風治散(第2類医薬品)」)をゆっくりと飲むと、体が温まってきます。
葛根湯の原料の一つ、葛根はその名からわかるように、葛の根の皮を取り去ったものです。これを精製すると葛粉になります。
普段台所にある食材で、お手軽に体を温める飲み物を作りたい場合は、飴湯を作ってみてはいかがでしょうか。水で溶いた片栗粉に、砂糖、お好みでおろし生姜を入れてゆっくり熱を加えると飴湯が出来ます。葛湯に似た、とろみのある、温かい飲み物です。砂糖の代わりに、はちみつ、または黒砂糖を入れてもおいしいです。小腹が空いた時の間食にお勧めです。子供のころ、冬に母が飴湯をたびたび作ってくれました。なつかしいおやつです。(注1、注2)
けやき堂薬局では、冷え性の改善に役立つ漢方として、婦人宝(第2類医薬品)をお勧めしています。胃腸の強さが普通か、丈夫な方向けのお薬です。婦人宝の商品名から連想すると、女性向けとなっていますが、冷えを自覚している方であれば、性別に関係なく服用出来ます。冷え性を自覚する男性がお飲みになられても、効果があります。
お客様おひとりおひとりの生活背景や体質に応じて漢方の選薬や、調合を随時行っています。ご希望の方は、お気軽にカウンセリングのご予約をお願いいたします。
冬場も健やかに過ごせる体づくりを行いましょう(岡北)。
【補足】
注1 薬膳からみた、葛粉と片栗粉の性質の違い ※2
葛粉⇒葛のでんぷん;涼性、寒邪(寒気)の発散。寒気をとる働きがあります。
片栗粉⇒じゃがいものでんぷん;平性、気を補う。脾胃(胃腸の働き、機能)を良くする。気を補う。
注2 くず粉は、葛の根のでんぷん質です。ジャガイモのでんぷん質である片栗粉も、水で溶いた後、熱を加えると、ご存じの通り、とろみが出ます。くず湯と似た食感です。
とろみのある食べ物は、液体中で対流が小さくなりますので、保温性が高く、冷めにくくなります。冬に食べる料理として、あんかけなどのとろみの多い食事が好まれるのは、このためです。
【参考書籍】
※1 参考 NHKきょうの健康 2022.12
※2 薬膳・漢方 食材&食べ合わせ手帖 (監修)喩靜、植木もも子


【ブログ】「冷え・不眠・疲れ…秋から冬の“なんとなく不調”に備える」
今年の夏は猛暑が続き、冷たい飲食物や冷房の使用、シャワー中心の入浴などで、知らず知らずのうちに内臓が冷えてしまった方も多いのではと思っています。
季節の変わり目は、疲れの出やすい時期です。これから迎える冬に備えて、体をしっかり調えることが大切です。温かい飲み物や食事を心がけ、湯船に浸かる入浴や足湯で体を温めましょう。
十分に明るい自然光(直射ではない)で、ピンクの生き生きした色なら、内臓の冷えは少ないでしょう。紫がかった色の場合は、冷えのサインかもしれません。
東洋医学では、舌の色や形状、つや、舌苔の色、形質は体内の変化を知る「ものさし」の一つとされています。
漢方薬剤師に客観的にみてほしいと希望される方は、当店に電話予約(電話・通話料無料 0120-58-5014)の上でお越しください。
脈波・コロトコフ音記録計で健康チェックされることも可能です。事前予約をお勧めしていますが、当日でも空きがあればご案内可能ですので、お声をおかけください。
秋から冬にかけての体調管理に、体を温める他に、質の良い睡眠とバランスの取れた食事を心がけましょう。
筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構の柳沢正史教授によると、睡眠には「質」と「ちょうどよい長さ」の両方が必要とのこと。10〜20代は8時間、40〜50代は7時間、70代では6時間が目安とされています。高齢になると睡眠が浅くなり、夜間に目が覚めることも増えますが、それは自然なことだそうです。
心身の健康を保つのに必要な睡眠時間に個人差がありますが、目覚めがすっきりしているなら、それが自身に合う睡眠時間です。
冬に向けて、部屋の温度管理にもご留意ください。寒い家で寝る人は、睡眠障害の確率が1.4倍増えます。日本サステナブル建築協会によると、冬場はリピングの温度が18℃あると、スムーズな入眠につながるそうです。
体を保温し、部屋を暖かくして眠ることで寒さによる中途覚醒も防げる、と私(岡北)は考えています。
これからの季節の過ごし方に、ぜひ参考になさってください。(岡北)
参考書籍:書籍「快眠法の前に いまさら聞けない 睡眠の超基本」柳沢正史(監修)

【ブログ】胃のデリケートな方の食事・生活養生法(秋)
夏の疲れは、夏の終わり~秋にかけ、一気に表れることがあります。食欲不振や疲れやすさ、下痢、軟便などの症状が出てきやすいです。
特に胃の弱い方は注意が必要です。胃の弱い方は、1度の食事で、例えば定食もの 大人一人前を残さずにしっかりと食べるのを重視することよりも、少量ずつで良いので、バランスのとれた食事をよく噛んで摂ることの方が大切です。
さらに食べ物からの栄養をしっかりと吸収して、体じゅうにそれらを行き渡らせるようにするために、「松寿仙(しょうじゅせん;第3類医薬品)」を継続してお飲みいただくと、血色が良くなり、体力や持久力の向上に期待できます。
今年の7、8月は特に暑く、40度近い気温の日が続きました。室内で過ごす時間の多かった方もいらっしゃると思います。
過ごしやすい時間帯を利用して、食後30分以上経った頃に、20分程度の散歩に出かけてみませんか。胃のデリケートな方や睡眠不足の方は、食後に眠くなりがちですが、歩くことで気分がリフレッシュし、心地よさを感じられるでしょう。
運動することが苦手とおっしゃる方は、まずは3分程度、普段着のままで、スニーカーなど歩きやすい靴を履いて、家の周辺を歩くことから始めてみましょう。毎日少しずつ続けることが大切だ私は考えています。
歩く際には、少し早歩きを意識すると(心臓から)血液を1回に拍出する量が増え、心肺機能が強化されます。これにより、体力の向上、生活習慣病の予防など、健康を守ることに役立ちます。
けやき堂薬局では、血流計(脈波・コロトコフ音記録計)を使って1回拍出量の測定も可能です。ちなみに、体脂肪1キログラムを消費するには7200キロカロリー使うことが必要とされており、あんぱん1個(約330キロカロリー)を消費するには、約80分のウオーキングが必要とされています(NHKきょうの健康2024.1より)。ダイエットを目標にされている方は、食生活の改善とともに、継続的な運動を心がけましょう。(岡北)

【ブログ】夏野菜 野菜の栄養を多く摂取する、ひと工夫とは?
夏野菜について; 特に体の熱を取る食材や、野菜の色が濃くビタミンや抗酸化物質(カロテンやポリフェノールなど)を豊富に含む食材が多いです。さらに、ネバネバとした成分(ペクチンなど)に富むオクラやモロヘイヤ、ツルムラサキのように、整腸作用や糖の吸収を遅らせて血糖値の上昇を抑える働きのある食材もあります。これらの食材は、暑さで疲れた胃腸や体力の回復に役立ちます。
植物は自らの意志で動くことができないので、自身で生み出す成分によって外敵から身を守っているといわれています。太陽の光を猛烈に浴びても植物は癌にならないことで知られています。紫外線や虫などから身を守る有益な化学物質のことを「ファイトケミカル」と呼ばれ、抗菌、抗炎症、抗酸化作用などあることが知られています。これらはビタミンやミネラルとは異なる成分で、色や香り、苦味(アク)のもとになっています。
生野菜で食べることよりも加熱して煮汁ごと食べることの方がファイトケミカルを多く摂取できます。
野菜に含まれている、ビタミンCも野菜を煮て、スープにしている場合は、ビタミンEやアントシアニンなどのファイトケミカルといった抗酸化物質と共存しているため、加熱しても分解されずに大半がスープの中に残っているそうです。(書籍「最強の野菜スープ」 前田浩(著)より)
激しい暑さで野菜の生育には大変な環境だと思いますが、今のところ野菜を比較的入手しやすく、献立にも取り入れやすいですね。
私は、キャベツ・人参・玉ねぎなどの常備野菜や、冷蔵庫に買い置きしている食材を使ってスープにし、野菜を摂るように心がけています。野菜スープや味噌汁を含め料理の味付けが控えめなので家族から、「健康食だね」とよく言われます。薄味なため、夫が自分の皿に調味料を足している姿を見ることもありますが、「腎臓のためにも薄味がいいのよ」と言いながら、目をつぶっています。我が家では、家族揃って食事をするのは週に2~3回ほど。その時間が最近の出来事や予定を語り合うひとときです。(岡北)
【ブログ】夏を快適に過ごすための漢方の知恵、身近な食材
二十四節気では、今年の夏至は6/21-7/6、立秋は8/7-8/22。暦の上ではあと1か月ほどで秋とはいえ、日本の夏はこれからが本番ですね。
高温多湿の気候により、体内に熱がこもりやすく、ほてりやのぼせ、頭痛、気の高ぶり、不眠といった不調を起こすことがあります。こうした症状を防ぐには、体にこもった熱を冷ましたり、発散したりする工夫が大切です。そうは言っても、冷房の効かせすぎや冷たい飲食物の摂りすぎは、内臓を冷やして働きを鈍らせ、むくみやだるさ、疲れやすさの原因にもなります。
中国医学では、夏の高温による病気や症状の原因のことを「暑邪(しょじゃ)」、湿度による同じく原因のことを「湿邪(しつじゃ)」と呼びます。これらが体に与える影響を考慮し、余分な熱や湿を取り除く食材や、発散を助ける食材を食事に取り入れることを勧めています。
体の熱を冷ます食材には、ナス、トマト、キュウリ、ゴーヤ、冬瓜、豆腐、スイカ、緑豆もやし、ミント、緑茶、レンコン、菊花などがあります。これらは常温、または加熱して摂ることで体を冷やしすぎるのを防ぎます。
一方、体の熱の発散を助ける食材にはネギ、生姜、紫蘇の葉、ミョウガなどがあり、これらは体を温める作用もあるため、熱を冷ます食材と組み合わせて摂るとバランスがとれます。また、新陳代謝を促し、体の熱を外に逃しやすくするためにも、しっかりと湯船に浸かる入浴を心がけましょう。冷房の効いた室内に長くいる方や冷えやすい体質の方は、先ほど挙げた生姜やネギなどの温性の食材を積極的に取り入れましょう。
漢方の選薬や過ごし方のことで気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください(事前に要予約)。




2025年7月4日
【コラム】けやき堂薬局の健康相談・カウンセリング
けやき堂薬局では、ご予約くださったお客様には落ち着いた環境の中でお話しいただけるよう個室でじっくりと健康相談を伺っています。私たちからお客様にお薬や生活習慣を押しつけたり、無理にプライベートなことを聞き出したりすることはありません。お客様の生活背景や考え方を尊重し、その方自身が「気づき」を得られるカウンセリングを目指しています。
なお、「しっかり病気を治したいから、必要な養生を教えてほしい」というご希望の方には、体質や現在の症状をふまえた具体的な養生法をお伝えしています。必要に応じて、脈波・コロトコフ音記録計でチェックしたり、舌の色・形・舌苔なども併せて確認したりして、的確にご提案をするよう努めています。
健康相談は予約制となっております。ご希望の方はお気軽にお声がけください。(岡北)