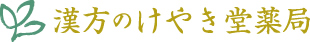【ブログ】夏を快適に過ごすための漢方の知恵、身近な食材
二十四節気では、今年の夏至は6/21-7/6、立秋は8/7-8/22。暦の上ではあと1か月ほどで秋とはいえ、日本の夏はこれからが本番ですね。
高温多湿の気候により、体内に熱がこもりやすく、ほてりやのぼせ、頭痛、気の高ぶり、不眠といった不調を起こすことがあります。こうした症状を防ぐには、体にこもった熱を冷ましたり、発散したりする工夫が大切です。そうは言っても、冷房の効かせすぎや冷たい飲食物の摂りすぎは、内臓を冷やして働きを鈍らせ、むくみやだるさ、疲れやすさの原因にもなります。
中国医学では、夏の高温による病気や症状の原因のことを「暑邪(しょじゃ)」、湿度による同じく原因のことを「湿邪(しつじゃ)」と呼びます。これらが体に与える影響を考慮し、余分な熱や湿を取り除く食材や、発散を助ける食材を食事に取り入れることを勧めています。
体の熱を冷ます食材には、ナス、トマト、キュウリ、ゴーヤ、冬瓜、豆腐、スイカ、緑豆もやし、ミント、緑茶、レンコン、菊花などがあります。これらは常温、または加熱して摂ることで体を冷やしすぎるのを防ぎます。
一方、体の熱の発散を助ける食材にはネギ、生姜、紫蘇の葉、ミョウガなどがあり、これらは体を温める作用もあるため、熱を冷ます食材と組み合わせて摂るとバランスがとれます。また、新陳代謝を促し、体の熱を外に逃しやすくするためにも、しっかりと湯船に浸かる入浴を心がけましょう。冷房の効いた室内に長くいる方や冷えやすい体質の方は、先ほど挙げた生姜やネギなどの温性の食材を積極的に取り入れましょう。
漢方の選薬や過ごし方のことで気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください(事前に要予約)。




2025年7月4日
【コラム】けやき堂薬局の健康相談・カウンセリング
けやき堂薬局では、ご予約くださったお客様には落ち着いた環境の中でお話しいただけるよう個室でじっくりと健康相談を伺っています。私たちからお客様にお薬や生活習慣を押しつけたり、無理にプライベートなことを聞き出したりすることはありません。お客様の生活背景や考え方を尊重し、その方自身が「気づき」を得られるカウンセリングを目指しています。
なお、「しっかり病気を治したいから、必要な養生を教えてほしい」というご希望の方には、体質や現在の症状をふまえた具体的な養生法をお伝えしています。必要に応じて、脈波・コロトコフ音記録計でチェックしたり、舌の色・形・舌苔なども併せて確認したりして、的確にご提案をするよう努めています。
健康相談は予約制となっております。ご希望の方はお気軽にお声がけください。(岡北)


【ブログ】ストレスや感情の変化と胃腸の不快感
日々の生活の中で、ストレスや感情の変化が私たちの体にさまざまな影響を与えます。特に、胃腸の不快感は多くの人が経験する症状のひとつです。ストレスが要因のみぞおちのつかえや張り、胃痛、腹痛、食欲減退、下痢など(1つでも当てはまるなら)中国医学では、「肝胃不和(かんいふわ)」、又は「肝脾不和(かんぴふわ)」の状態と考えます。
これらの症状を和らげるためには、日常生活を送る中で、気(元気の気)の巡りを整え、血流を良くすることです。
具体的な方法として、適度な運動や、深呼吸、歌を歌う、アロマセラピーなどを取り入れることで、自律神経のバランスを整えることが期待できます。最近は、胃脳相関といって、精神的な状態と胃の働きが関連しあうことが言われて注目されています。
お客様から「胃を先に整えるべきか、自律神経を先に整えるべきか」とご質問をいただくこともあります。こうしたお悩みに対しては、私はまず胃を整える漢方を選ぶ、又は最初から両方に働きかける漢方を選びます。
具体的には松寿仙をはじめ、ササイサン・紫華栄(しかろん)や四逆散、逍遥散(しょうようさん)、藿香正気散(かっこうしょうきさん)といった漢方薬や自然薬(自然の恵みを用いた薬)をご提案しています。
「今のままではもっと体調が悪くなるのでは…」と不安を抱えている方もおられます。その中でも、漢方を飲みながらご自身の体と向き合い、少しずつ変化を感じていただくことで、「何とかなりそう」と前向きになっていく方が多いです。そうした気持ちの変化こそ、回復への第一歩と感じています。(岡北)

【ブログ】初夏~夏を快適に過ごすセルフケア
気温が上がると汗をかいたり喉が渇いたりするので、水分補給の機会が増えます。冷たい飲み物を避け、のどを潤すことを意識して一口ずつ摂取しましょう。お腹を冷やさないことが、夏を元気に過ごすポイントです。初夏から夏、秋へ、季節は途切れることなくつながっています。現在の養生(セルフケア)が、次の季節を快適に過ごすための鍵となります。
また、1日の中で寒暖差が大きいため、体温調節のしやすい服装でお出かけしましょう。薄着を避け、体の保温を心がけることが大切です。下半身の冷えは腸の働きに影響を与え、下痢や慢性的な便秘につながることがあります。夜はなるべく湯船に浸かり、体を温め、血流も良くして1日を締めくくりましょう。

【コラム】 お客様と当店のスタッフ
漢方のけやき堂薬局は、2006年の開業以来、お客様に支えられ、18年以上の年月を歩んでまいりました。開業当初からお越しいただいているお客様や、3世代にわたってご利用のご家族もいらっしゃり、心から感謝申し上げます。
現在一緒に働いている女性スタッフは、複数在籍しておりますが、皆10.5年以上の勤務経験があり、お客様と共に長い時間を過ごしています。
当店の特徴の一つは、通販メーカーや一般的なドラッグストアでは取り扱っていない、漢方専門ならではのお薬、商品をご用意している点です。そのため、「この漢方が欲しい」と指名して来店されるお客様も多くいらっしゃいます。
もちろん、「この薬を飲めば100%治る」というものはありませんが、多くの選択肢の中から「自分の体に合っている」とお感じのお薬を求めてくださり、リピートしていただいている方もいらっしゃいます。
また、年齢とともに体の様子が変化することがあります。妊活、健康寿命を延ばしたいなどというご希望や目標に応じて、カウンセリングにてお薬の見直しを行っています。漢方の中でも滋養強壮に役立つ薬や食品は継続して服用できる安全性の高さと、有効性が魅力です。不易流行で改良が進んでいる商品もあります。
私たちは、ニュースレターで最新情報や、一番お伝えしたい内容を発信しています。また、LINEでは月に1回程度、ニュースレターの概要や異なる視点からの情報を発信しています。
これからもお客様の健康と笑顔を支える存在であるよう努力してまいります。
2025年4月吉日 岡北


春の過ごし方 冬に溜めた老廃物を出す
春は中国医学で「肝(かん)」の季節とされ、体内のデトックス(老廃物を出すこと)が自然と促進される時期です。五行学説では、春は「木」に属し、「肝」と特に深いつながりがあります。「肝」は気血の巡りを助け、毒素の排出をサポートする働きがあると考えられています。
※ 五行学説については、こちら→ (前回の記事)中国医学と五行(ごぎょう)
春は、「肝」をケアすることで、心身のバランスを整えるのが中医学の知恵です。
■食生活: 「肝」の働きを助ける食べ物:香りのよいもの。解毒を助けるもの。胃腸の働きを良くするもの。いずれも旬にとれるものが良いです。
〇香りの良い食材 セロリ、みつば、パセリ、春菊、かんきつ類 など
〇疲れやすい、胃腸が弱いなど「気虚(ききょ)」にお勧めの食材 消化の良い鶏肉や鯛など
〇「肝」に働きかけ、解毒代謝を促進する食材 セロリ、ほうれんそう、ゴボウ、ウド、タケノコなど
■リラックス: ストレスは「肝」に負担をかけるため、自然散策や歌を歌うことなどで気を巡らせる時間を作りましょう。
■適度な運動: 軽いストレッチやウォーキングで身体を動かすことで、気血(きけつ:元気の気と、養分を含む血液)の流れがスムーズになります。
この機会に心身の「デトックス」を意識してみてはいかがでしょうか?(岡北)
中国医学と五行(ごぎょう)
中国に古くから伝わる考え方、哲学の一つに、五行学説があります。
五行学説は、宇宙に存在するすべての事物・事象を「木(もく)・火(か)・土(ど)・金(こん)・水(すい)」の五つの要素に分類し、それらの相互関係を通じて解釈する理論です。この学説は、臓腑(内臓)の働きや病理(病気の原因)の解釈にも応用され、人体のバランスを理解する上で重要な役割を果たします。例えば、五行(木・火・土・金・水)は五臓「肝(かん)、心(しん)、脾(ひ)、肺(はい)、腎(じん)」や五季(春・夏・梅雨、季節のはざま・秋・冬)に対応し、それぞれが相生(助け合う)や相克(抑制し合う)という関係で結びついています。
この五行学説は古代中国の医学書「黄帝内経(こうていだいけい)」に記され、中国医学(漢方医学)の基礎として現在も使われています。
五行という言葉になじみがなくても、「五臓六腑(ごぞうろっぷ)にしみわたる」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。例えば、冷たいビールを一口飲んで「ああ、五臓六腑にしみわたる!」と声を上げる人もいますよね。この言葉は、五行の五臓に由来していると言われています。おいしい飲み物や食べ物を口にした際に、その感動が内臓全体、そして全身に染み渡るような感覚を表現しています。
五行学説で、宇宙に存在するすべての事物・事象を説明するということに、理屈っぽく、こじつけに感じる人もいると思います。しかし中国医学を理解する上では、五行説は基礎となりますし、紀元前の昔に考えられているのに、体系的、かつ理論的にまとめられています。黄帝内経を著した古代の中国の作者に、頭が下がる思いです。(岡北)

神経疲労が多くて、体が疲れやすい方へ 元気になる食べ物・過ごし方
寒さが少しずつ和らいで雨の降ることが続いています。暖かい陽気の後に、気温が下がることもあります。
つい先日、定期的に連絡下さっているお客様から相談があり、「体を温めるように気を付けているけれども、今、体が芯から冷えて温まってこないし、元気が出ない」とおっしゃっていました。
気温が上がったり下がったりを繰り返す中で、気温が下がった後、再び体温を上げて維持することに体力を使っているのでしょう。私のこれまで受け持ってきた健康相談の経験から、職場や家族など周囲の人に神経を遣うことが多い人は、肉体的な疲れも出てきやすい、と感じています。
東洋医学(中医学)では、気は、元気の気で、活動エネルギーの元であり、体を温める作用があるとしています。普段から、神経を使い、気をたくさん消費していることで、目には見えませんが、気の貯えが少なくなり、活動量は多くなくても、冷えやすく、心身もまた疲れやすいのだと思います。その結果、寒暖差があって元気が出ないのでしょう。
春の神経疲労への養生法は、体温を衣服で調節すること、体の内側からも温めて、血流を良くすることです。また、胃腸を整えておくことも、(体温調節に働く)自律神経の働きを良くすることに役立ちます。食べ物から気(栄養物)を受け取っているので、消化吸収の働きを良くしておくことが大事です。
胃腸の働きが弱っている場合は、他の症状を改善させることよりも胃腸を整えることを優先して考えましょう。近年、胃脳相関、腸脳相関があることが医学的に分かっていて、消化器の働きと精神活動、脳の神経の作用が互いにコミュニケーションを取り合っていることが注目されています。
春のお勧めの食材(食養生);
いらいらしやすい、気持ちが落ち込む、感情が乱れやすい場合: シソ、春菊、セロリ、三つ葉、かんきつ類(レモン、オレンジ)
よく眠れない場合、血を作る食べ物: アサリ、ナツメ
胃の調子が悪い場合: 豆類、じゃがいも、鶏肉、キャベツ
春のお勧めの過ごし方(生活養生);
日光浴、軽めの運動、湯船に浸かること、深い呼吸を心がけることです。
これらをまず出来ることから取り入れて、少しずつでいいので続けてみてください。
一般的に、胃腸の働きを整えて気を補う目的で用いる漢方薬は、補中益気湯、又は 帰脾湯(きひとう)、香砂六君子湯(こうしゃりっくんしとう)など。
いらいら、不安、不眠には、香蘇散(こうそさん)、又は 逍遥散(しょうようさん)、芎帰調血飲第一加減(きゅうきちょうけついんだいいちかげん)などです。
けやき堂薬局では、普段から自然薬や漢方で自然治癒力を上げておく体つくりをお勧めしています。そうしておくと多少、気などを消耗することがあっても、回復するのが早く、症状を改善する漢方を後から取り入れた場合も、少量で効果があらわれるでしょう。(例えば、春の頭が覆いかぶさるときにのむ、香蘇散など)
健康寿命を延ばしたい方、体調不良をお感じの方など、お気軽にご相談ください。
慢性的な症状の方は、まずご予約をお願いいたします。
カウンセリングで丁寧にお話を伺い、必要に応じて選薬いたします。(岡北)
公開日:3月7日



自然治癒力を高める
暦の上では春になりましたが、全国的に寒さが厳しいですね。寒さが緩んでいる日も、気温差が大きいので暖かい服装で、外出をしましょう。体の内側から体を温める食材を摂ったり、漢方を飲んだりすることで陽の気(体を温めるエネルギー)を守ることが出来ます。寒邪を発散させ、体を温める食材には、にら、ねぎ、しょうが、とうがらし、シナモン、さんしょう、玉ねぎ、よもぎなどです。
私たちの体には恒常性が備わっています。恒常性と自然治癒力は、どちらも体の健康を保つための重要な仕組みですが、異なる役割を持っています。
恒常性は、体を一定の安定している状態にまで保とうとする機能のことです。血圧や血糖値、体温などが挙げられ、自律神経(意思で制御できない)、ホルモンの調整、体性神経(運動機能や反射など、意思で制御できる)が協力して調整しています。例えば、暑熱時には、血管が広がり、汗をかいて体温を下げます。反対に、寒冷時には血管の収縮・ふるえなどが生じて熱が産生され、体温を上げます。
自然治癒力は、けがや病気の際に、体を修復する機能です。免疫細胞がウイルスや細菌を見分けて闘い、回復を図ります。
簡単に言うと、恒常性は体の状態を安定させるための仕組みであり、自然治癒力は体が病気やけがを治す力です。どちらも健康を維持するために重要な役割を果たしています。
薬の効果は、治療薬の効果(治療効果)+自然治癒力+プラセボ効果(心理的な要因)によって発揮されると言われています。
松寿仙は、恒常性を保ち、自然治癒力を高める、滋養強壮の効果があります(参考:松寿仙の添付文書)。松寿仙は、アカマツ、クマザサ、薬用人参の3つの天然成分から作られていて、これらの成分が体のバランスを整え、自然治癒力を高める働きをします。そのため、病院などの治療薬を服用中であっても、併用することで、効果を発揮しやすくなるでしょう。
松寿仙は副作用が少なく、長期間服用しても安心な点も魅力です。
自然治癒力を高めるためには、バランスの良い食事、十分な睡眠、適度な運動なども大切です。松寿仙は、これらの健康的な生活習慣を補う役割を果たしています。
けやき堂薬局にお越しになられたお客様でご希望の方に、温かい松寿仙をご用意しておもてなしをしています。店内では、松寿仙をウーロン茶で割っており、初めて飲む方も飲みやすいとおっしゃってくださいます。
赤ちゃんから、妊活中、妊娠中、授乳中、働き盛りの方、シニアの方まで、家族みんなが飲めます。
20年以上、我が家では義父、夫、小学生の息子、私で飲んでいます。(岡北)
冬季うつ対策 日常生活の工夫と食べ物
秋、冬の間中、日の短い時期になると、意欲が低下する、何事もおっくうに感じる、たくさん寝ているのに、眠気を強く感じるのなら、冬季うつの症状かもしれません。
冬季うつは、学術的に言いますと、「季節性感情障害」の一種です。日照時間が短くなることで、神経伝達物質のセロトニンの分泌が著しく減少することが大きな要因と考えられています。冬季うつは、意欲の低下、日中に強い眠気を感じる、食欲が増して、甘いものや炭水化物をたくさん食べたくなる症状が起こります。そして、春になると、これらの症状が消失するのが特徴と言われています。
東洋医学では、この冬季うつの症状は、気血の不足によるものと考えられています。気血を補うには、胃腸のデリケートな方は、まず脾胃(消化管の消化吸収機能)を良くして食べ物の栄養素が吸収できるように整えることが大切です。脾胃の働きを助ける食べ物に、白菜、しょうが、キャベツ、人参、みかん、紫蘇などがあります。
気血を補う食材は、しいたけ、エリンギ、鶏肉、山芋、なつめ、牡蠣、ぶり、鮭、さばなどです。冬季うつになるとは炭水化物や甘い食べ物にかたよった食事になりやすいので、野菜や肉や魚、卵、豆類などのタンパク質も努めてバランス良くとるようにしましょう。
西洋医学では、「高度光療法」が行われています。5000ルクス以上の人工の光を浴びる方法で板状の光の出る特殊な装置を用います。
日常生活の工夫として、日光浴がお勧めです。太陽の光を浴びる方法にはポイントがあります。それは光が目に届くようにすることです。日中、屋外で過ごす時は、太陽の光を直接見ないように、1分間に10-20秒明るい方に視線を向けます。1日30分間を目安にします。太陽の出ている時間なら、いつでも出来ます。(直接、太陽の光を直接見ると、目の組織が傷ついて視力が低下することなど起こるので直接見ないようにご注意ください。)
屋内で行うには、窓から1m以内の明るいところで30分間ほど過ごします。時々、視線を上に向けて目に光を届けるようにします。太陽の光が斜めに射す朝や夕方が良いと言われています。自律神経の働きを整えるために、ウオーキングやストレッチ、ラジオ体操など軽い運動を取り入れましょう。
また、体の保温をしましょう。東洋医学では、冬は腎(成長、発育、老化と深いかかわりがある)の季節といわれています。腎は寒さが苦手なため、体を冷やすことは、腎の弱りにつながり、様々な不調をもたらすことがあります。寒さのために、体を温める「陽の気(エネルギー、パワー)が消耗しやすい時期ですので、寒さなどの邪を発散させる食材や体を温める食材を摂ることがお勧めです。
発散作用がある辛みのもの、体を温める食材は、しょうが、ねぎ、にら、よもぎなどです。「腎」の精気(生命力に関わる基礎物質とパワーのこと)を補い、陽の気を高める食材に、羊肉、牛肉、ししゃも、にら、長ネギなどがあります。
(以上、参考資料 きょうの健康2024.11、2017.1、クラシエ Kampoful Life サイトより)
漢方、自然薬では、帰脾湯、紫華栄、安静錠などがあります。食事や生活の工夫を行ってもなかなか良くならない場合は、ご相談ください(要事前予約)(岡北)。